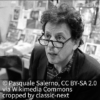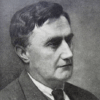アリス=紗良・オット(ピアノ)/フィールド:夜想曲第4番
作曲:ジョン・フィールド
(John Field 1782 – 1837、アイルランド)
曲名:夜想曲第4番 イ長調 H.36
(Nocturne No.4 in A major, H.36)
ジョン・フィールドはアイルランド出身の作曲家・ピアニストですが、おそらくこれまではピアノを習っていた方や、かなりのピアノ好きの方にしかフィールドの作品は知られてこなかったのではないでしょうか。
ところが近年、デッカやドイツ・グラモフォンといったメジャーなレーベルから夜想曲集の録音がリリースされたことで一般的なクラシックファンからの注目も広く集めるようになってきているようです。
そこで今回は、フィールドの夜想曲のなかから優しい雰囲気で聴きやすい第4番を選んでみました。
夜想曲とロマン派音楽
ピアノのための夜想曲(ノクターン)といえば、やはりショパンやフォーレが有名ですが、ジョン・フィールドはその創始者として知られています。
フィールドの「夜想曲」の特徴は、比較的メロディーが明確で、印象としては優雅であったり、歌心が豊かであったり、まさに夜、想いをめぐらせるような曲と言うことができるでしょう。
ジョン・フィールドが活動した時代は、成熟した古典派音楽の時代から徐々にロマン派へと移行する時代でした。つまり、調和やバランスを重んじる風潮から徐々に感情を音楽にのせて表現することに価値を見出していった時代です。
フィールドの夜想曲はショパンやリストに大きな影響を与え、さらにはメンデルスゾーンやシューマンといったロマン派の名作曲家が背中に押されるようにして、それぞれの名作を残していきました。
優雅で歌心が豊か、かつ単一楽章といった特徴のフィールドの夜想曲は、ちょうどロマン派の音楽がそれまでの時代の形式にとらわれずに感情の豊かさを求めた時代にピッタリだったのかもしれません。
ピアノとフォルテピアノ
冒頭の動画は、ピアニストのアリス=紗良・オットによる演奏の動画です。音を少し短めに切るノンレガート(ポルタート)という奏法がとても印象的です。ノンレガートによって音の粒がはっきり聴こえるようになります。どこでノンレガートを使っているか、どこで使っていないかを意識して聴いてみるのもよいでしょう。
ところで、冒頭の動画でアリス=紗良・オットが弾いているのは現代のピアノ、モダンピアノですが、ジョン・フィールドの時代はピアノという楽器が大きく発展した時代でもありました。現代のピアノがある時代から見れば、当時は発展途上の時代とも言えるかもしれません。現代のピアノであるモダンピアノに対して、当時、1700年代から1800年代前半にかけて製作されていたピアノはフォルテピアノと呼ばれています。当時はまだ現在のモダンピアノはありませんでしたから、モーツァルトやベートーヴェン、ショパンやフィールドたちはこうしたフォルテピアノを弾いていたというわけです。
最後に、ベルギーの演奏家で音楽学者でもあるリゼロッテ・セルスがフォルテピアノで同じ第4番の夜想曲を演奏した動画を紹介しましょう。
動画のタイトルに「Graf fortepiano 1826」とありますので、ウィーンのグラーフ社の1826年製のフォルテピアノかと思います。1826年に製作されたオリジナルなのかレプリカなのかは不明ですが、フィールドの夜想曲第4番の楽譜が出版されたのが1817年ですから、それから9年後に製作されたモデルのフォルテピアノです。
当時の楽器、古楽器を使う演奏は、1970年代あたりから古楽器への回帰の流れを受けて盛んになったようです。もちろんフォルテピアノもオリジナルやレプリカを用いての演奏や録音がおこなわれています。製造上、現代のピアノよりも金属の使用が少ないため、どことなく「木」の鳴り・響きが感じとれるのがフォルテピアノの音色の大きな特徴です。
リゼロッテ・セルス(フォルテピアノ)/フィールド:夜想曲第4番