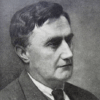キアラ・バンキーニ(ヴァイオリン、指揮)、イェスパー・クリステンセン(チェンバロ)、アンサンブル415/ゲオルク・ムファット:『調和の捧げもの』よりコンチェルト・グロッソ第5番ト長調
上の動画はこのサイト用に作成した再生リスト(YouTube)の1曲目です。そのまま最終楽章まで視聴できます。
作曲:ゲオルク・ムファット
(Georg Muffat 1653 – 1704、フランス→ドイツ)
作品:『調和の捧げもの』よりソナタ第5番 ト長調
(Sonata No.5 in G major from “Armonico tributo”)
ゲオルク・ムファットはフランスに生まれ育ち、オルガン奏者として音楽家人生をスタートさせたあと、イタリア、オーストリア、チェコ、ドイツとヨーロッパ各地を渡り歩いた作曲家です。そうしたなかで、フランス音楽とイタリア音楽のそれぞれのよさをドイツの音楽と融合させて新たな地平を開いた作曲家と言うことができるでしょう。
なお、ムファット本人はドイツ人を自認していたこと、また音楽作品名辞典の表記にならって、このサイトでも国別の作曲家としてはドイツの作曲家と分類しています。
また、名前の表記については、ネット上でも「ムファット」と「ムッファト」に分かれているようですが、カナの発音上「ムッファト」であるとは言い難いため、ここでは「ムファット」と表記します(Muffat ですから本当はドイツ語の発音にもっとも近いカナ表記は「ムッファート」かと思うのですが)。
ムファットは日本ではまだそれほど知られていない作曲家かと思いますが、その作品は多くの演奏家によってとりあげられていて、聴く人の心を魅了しています。
ここで、2つの知識の前置きをしておきましょう。
知識の前置き①『調和の捧げもの』
まずは『調和の捧げもの』についてです。
『調和の捧げもの』は1682年に5曲の室内ソナタ集として出版されました。
ムファットはその後1701年に『調和の捧げもの』の5曲にあらたに7曲を加え、さらにそれぞれ楽器編成を増やしたり改変をして、12の合奏協奏曲集『熱意と好みで選ばれた器楽音楽(Ausserlesene mit ernst und lust gemengte Instrumental-Music)』として出版しました。
現在、いろんな演奏家が録音を残していますが、やはりオリジナルのほうの『調和の捧げもの』の5曲が演奏されることがほとんどです。
ここでとりあげる第5番は、以下の5曲から構成されています。
1. Allmanda Grave (アルマンド – グラーヴェ)
2. Adagio(アダージョ)
3. Fuga(フーガ)
4. Adagio(アダージョ)
5. Passagaglia Grave(パッサカリア – グラーヴェ)
知識の前置き②「室内ソナタ」と「コンチェルト・グロッソ」
次に楽曲のスタイルについてです。
『調和の捧げもの』は室内ソナタ集なので、それぞれの曲は「ソナタ Sonata」と表記されています。
『熱意と〜』は合奏協奏曲集として出版されたので、それぞれの曲は「合奏協奏曲 Concerto grosso(コンチェルト・グロッソ)」または「協奏曲 Concerto(コンチェルト)」と表記されています。
では、「室内ソナタ」と「コンチェルト・グロッソ」は具体的にどう違うでしょうか。
「室内ソナタ」はバロック時代に流行した楽曲形式で、メロディーを担当する楽器と、伴奏を担当する通奏低音(ここではシンプルに、1人か2人の演奏者による「低音楽器による伴奏」とお考えください)によって演奏される室内楽曲の形式です。
ムファットの『調和の捧げもの』では、2台のヴァイオリンがメロディーを担当します。伴奏は2台のヴィオラと、チェロを含む通奏低音が担当します。
一方「コンチェルト・グロッソ(合奏協奏曲)」は、ソロを担当する複数の楽器(コンチェルティーノ)と、合奏を担当するその他の楽器(リピエーノ)がそれぞれ交互に演奏されるのが大きな特徴です。ときには一瞬だけソロが顔を出したり、数小節おきにソロと合奏が入れ替わったりします。ソロと合奏に分かれているという点では、たしかに「コンチェルト(協奏曲)」ですね。
通常は「室内ソナタ」よりは「コンチェルト・グロッソ」のほうが楽器編成は大きめです。冒頭に紹介した動画で「コンチェルト・グロッソ」と表記されているのは編成が大きめであることを考慮したものかもしれません。
ムファットがのちに編成を増やした『熱意と~』では、やはり2台のヴァイオリンと、チェロを含む通奏低音がソロ、伴奏の合奏はヴァイオリンからチェロまでの弦楽器が担当します。
ちなみに、「室内ソナタ」も「コンチェルト・グロッソ」も、ムファットがイタリアで出会って大きな影響を受けたという作曲家コレッリによって広く人気を得た楽曲形式だということも知っておいてよいかもしれません。
聴きどころ① 「2台のヴァイオリン」と「低音楽器による伴奏」
さて今回は知識の前置きが長くなってしまいましたが、そこで触れた「2台のヴァイオリン」と「低音楽器による伴奏」という点がまず聴きどころとして挙げられると思います。
「2台のヴァイオリン」と「低音楽器による伴奏」、これは室内ソナタの演奏スタイルです。
「2台のヴァイオリン」と「その他の楽器の合奏による伴奏」、これはコンチェルト・グロッソの演奏スタイルです。
2台のヴァイオリンによるメロディー、また、ハモったり追いかけたりなど、2台のヴァイオリンがそれぞれどのような関係性で演奏されるのか、そして低音楽器の伴奏が2台のヴァイオリンとどのような関係性をもちながら演奏されていくのか。2台のヴァイオリンによるソロと、その他の弦楽器による伴奏との対比が聴きどころのひとつです。
聴きどころ② パッサカリア
そしてもうひとつの聴きどころは第5番の最終楽章のパッサカリアです。前回のヴォーン・ウィリアムズの交響曲第5番に続いてまたパッサカリアが出てきました。
『音楽の捧げもの』はそれぞれの曲はごく短いものなのですが、この作品集のトリを飾る第5番のパッサカリアだけは演奏時間に10分を要するという大作です。
このパッサカリアが感じさせる壮麗さを、パリで学んだ作曲家リュリの影響とみることもできるでしょう。たしかに、リュリのいくつかのバレエやオペラの楽曲を連想させます。
そしてこの壮麗さはやはり室内楽サイズの編成よりは、弦楽アンサンブルの厚みを活かした大きな編成のほうがより魅力を引き立たせるのではないかと思います。
特に、パッサカリアは数小節を繰り返す箇所があり、楽譜では「1回目はソロで、2回目は合奏で」といった具合に指示されています。こういった箇所は大きめの編成による合奏のほうがメリハリのある演奏を楽しめるかもしれません。
また、このパッサカリアの後半には、跳ねるようなリズムに変化する箇所があります。これはスペインとイタリア発祥のチャッコーナという舞曲(フランスにとり入れられて「シャコンヌ」として親しまれるようになりました)をとり入れたものといわれています。この跳ねるようなリズムにあわせてパッサカリアの冒頭のメロディーが再現されるあたりはなかなかスリリングです。
終わりに
冒頭に紹介した動画で演奏しているのは、スイスのルガーノ出身のヴァイオリニスト、キアラ・バンキーニが率いるアンサンブル415です。アンサンブル415は残念ながら2012年に解散し、30年に渡る活動に幕を下ろしましたが、イタリア・バロック作品を中心に録音を残して人気を得ました。
さて最後に、第5番をムファットが改訂した『熱意と好みで選ばれた器楽曲集』ヴァージョンのパッサカリアをブレーメン・バロックオーケストラがライブ演奏を残していますのでご紹介しましょう。
『音楽の捧げもの』第5番は、『熱意と~』では第12番に変わりますが、ここでも大トリを務めています。「Propitia Sydera プロピティア・シデラ」というラテン語の副題がつけられていて、訳すと「恵みの星々」「慈悲深い星々」といったところでしょうか。また、最終楽章のパッサカリアは「チャコーナ(シャコンヌ)」に変わっています。
ブレーメン・バロックオーケストラ/ムファット:『熱意と好みで選ばれた器楽音楽』合奏協奏曲第12番「Propitia Sydera」よりグラーヴェ – チャコーナ