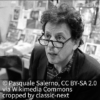マッシモ・パロンベッラ(指揮)、システィーナ礼拝堂聖歌隊/パレストリーナ:教皇マルチェルスのミサ
上の動画はこのサイト用に作成した再生リスト(YouTube)の1曲目です。そのまま全曲視聴できます。
作曲:ジョヴァンニ・ピエルルイージ・ダ・パレストリーナ
(Giovanni Pierluigi da Palestrina 1525? – 1594、イタリア)
曲名:ミサ曲「教皇マルチェルスのミサ」
(Missa Papae Marcelli)
パレストリーナは、クラシック音楽の時代区分としてはバロックのひとつ前の時代であるルネサンスの時代に活躍した作曲家です。
当時のイタリアだけでなく、ルネサンスの時代を代表する作曲家のひとりとして覚えておいてもよいかと思います。
そして今回とりあげる「教皇マルチェルスのミサ」はパレストリーナの代表作のひとつとして有名なのですが、ルネサンス時代の作品であるせいか、一般的な名曲集などにはなかなかとりあげられにくいのが現状のようです。
作品の背景について
さて、パレストリーナの「教皇マルチェルスのミサ」は、1567年に刊行された『ミサ曲集第2巻』に収められていて、近年の研究によって1562年には作曲されていたことがわかっています。ちなみにパレストリーナの『ミサ曲集』は第13巻まで刊行されています。
教皇マルチェルスとは、1555年に22日間だけカトリック教会の教皇に即位したマルチェルス2世のことを指します。よく「ローマ法王」という語を見聞きしますが、この「ローマ法王」と「教皇」はおなじ意味で、カトリック教会の最高位聖職者のことです。
「ミサ」の構成などを少し
「教皇マルチェルスのミサ」の構成は以下のとおりです。
1. Kyrie(キリエ)
2. Gloria(グロリア)
3. Credo(クレド)
4. Sanctus / Benedictus (サンクトゥス / ベネディクトゥス)
5. Agnus Dei(アニュス・デイ)
ミサ曲としてはとても基本的な構成をしていますので、覚えておいてもよいかもしれません。そして「キリエ」、「グロリア」などのタイトルはそれぞれの歌詞のいちばん最初の語句でもあります。
なお、サンクトゥスとベネディクトゥスは短いこともあってCDなどでは同じトラックにくくられることがあります。また、この「教皇マルチェルスのミサ」は最後の「アニュス・デイ」が二部構成になっています。
「教皇マルチェルスのミサ」は6声のための作品です。楽譜を見ると以下のようにパートが6つに分かれているのがわかります。
ソプラノ
アルト
テノール×2
バス×2
といった具合ですが、最後の「アニュス・デイ」の後半は7声になっています。
また、カトリック教会のミサ曲ですので、歌詞はラテン語です。
ラテン語の歌詞というものにはおそらく馴染みがないところかと思いますが、たとえば「キリエ」の最初の“キリエ・エレイソン”は“主よ、あわれみたまえ”という意味で、また、比較的よく出てくる「ドミヌス・デウス」は“主なる神”といった意味です。全体的に主イエス・キリストを讃えるような内容だと考えていただければよいかと思います。
聴きどころについて
「教皇マルチェルスのミサ」を聴いていただくとおわかりかと思いますが、最初の「キリエ」からしてとても聴き心地がよいというか、安らかといった印象を持つのではないでしょうか。
あるいは、全編そうなのですが、たとえば「キリエ」の冒頭や「クレド」の後半の特にラストで、他のパートに対してあるパートだけが細かく上下してハーモニー、メロディーが複雑に入り組んでいるように聴こえる、でも美しく聴こえる、という箇所があることに気づかれるのではないかと思います。
実はこの点がパレストリーナの作曲家としての手腕で、この安らかさをもたらす優美さや安定感といった特徴は後に「パレストリーナ様式」とまで呼ばれるようになりました。
また、他のパートに対してあるパートだけが細かく上下してハーモニー、メロディーが複雑に入り組んでいるように聴こえる、でも美しい、という点はパレストリーナがこだわった作曲技法で「線的対位法」とも呼ばれます。
大雑把な説明で申し訳ないのですが、こうした、それぞれのメロディーが同時に演奏されながら破綻することなく聴こえるという「対位法」は、パレストリーナが活躍したルネサンス時代からそのあとのバロックの時代に盛んに研究されました。この「教皇マルチェルスのミサ」からおよそ120年後に生まれ、対位法の大家として知られるヨハン・セバスティアン・バッハもまたパレストリーナから多大な影響を受けた作曲家のひとりでした。
対位法については、今回説明したような簡易な、必要最低限なとらえ方でもよいので頭の隅に置いておくと、今後の音楽の聴き方も変わってくるのではないかと思います。
フリーで見られる楽譜のリンクを貼っておきますので、もしよければ楽譜をご覧になりながら聴いてみてください。
Palestrina_Missa_Papae_Marcelli.pdf – ChoralWiki
システィーナ礼拝堂聖歌隊について
とりあげた動画のシスティーナ礼拝堂聖歌隊は、世界遺産としても有名なヴァチカンのシスティーナ礼拝堂での式典や行事で合唱を務めるための教皇個人用の聖歌隊として1400年代後半に設立され、世界最古の聖歌隊のひとつとして知られています。そして実は、パレストリーナ自身もこのシスティーナ礼拝堂聖歌隊のメンバーでした。
近年では、クラシック音楽レーベルの名門であるドイツ・グラモフォンからアルバムを発表しています。余談になりますが、最近のクラシック音楽のアルバムリリースには疎いのですが、ドイツ・グラモフォンが聖歌隊・合唱団単体による録音をリリースするのはかなり珍しいことのように思います。もともとドイツ・グラモフォンには合唱作品のアルバムは多くない印象ですので、今後もこういったリリースが続くのかどうか、興味深いところでもあります。