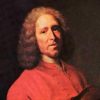A・テナーリア(オーボエ)、V・ヴァレンティ(トロンボーン)、C・ペトルッチ(ヴァイオリン)、M・トゥッリツィアーニ(コントラバス)、D・スクックーリア(ピアノ)、フランチェスコ・ラ・ヴェッキア(指揮)、ローマ交響楽団/レスピーギ:5声の協奏曲
作曲:オットリーノ・レスピーギ(1879 – 1936、イタリア)
曲名:5声の協奏曲
レスピーギの代表作といえば「ローマ三部作」です。クラシック音楽の名曲集にはほぼ必ず収録される曲ですので、お聴きになった方も多いと思います。ただ、この「ローマ三部作」の印象があまりにも強いため、その他の作品がなかなか顧みられない作曲家でもあります。
ここでとりあげるのは「5声の協奏曲」ですが、そもそも協奏曲のほとんど、特にロマン派までの協奏曲は、ピアノのための協奏曲(ピアノ協奏曲)やヴァイオリンのための協奏曲(ヴァイオリン協奏曲)といったように一種類の独奏楽器とオーケストラが組み合わされます。例外としては、モーツァルトのフルートとハープのための協奏曲、あるいはベートーヴェンのピアノとヴァイオリンとチェロのための三重協奏曲などが有名ですね。
協奏曲に関していえば、ロマン派後期あるいは近代になってからは、複数の種類の独奏楽器のための協奏曲が作曲されることは特別なことではなくなったと思います。つまり、時代が経過するにつれて協奏曲そのものがより高度に追求されていったということがいえるでしょう。
このレスピーギの「5声の協奏曲」はピアノのほかに弦楽器が2種類、管楽器が2種類(木管と金管で1種類ずつ)、あわせて5種類の独奏楽器が設定されています。すでにお気づきかとは思いますが、この作品では5種類の独奏楽器が5つの独奏パートを担っているので「5声の協奏曲」というわけです。
曲の構成はバロック時代に完成された協奏曲の特徴である三楽章構成にのっとっており、速めの第一楽章、真ん中の第二楽章がゆっくりなアダージョ、そしてまた速めの第三楽章で締めくくられる構成もオーソドックスな協奏曲の形式です。
先ほど、協奏曲そのものがより高度に追求されていった、と書きました。「5声の協奏曲」において、5つの異なる楽器とオーケストラがどのように組み合わされているか、それによってどのような聴こえ方になっているか、一曲のなかに聴きどころはたくさんあると思います。バロックや古典の伝統を大切にしつつ、イタリア近代音楽で試みられたひとつの挑戦のかたちを楽しんでいただければと思います。